6期鬼太郎振り返り企画。ここではエピソードにスポットを当てていきたい。
テーマ別傑作選
自選のベストエピソードを発表する前に、まずはテーマ別の傑作選を紹介。話数や順位を限定せずに選んだので、テーマによって選ばれたエピソード数に違いがあるが、以下に列挙したエピソードは見て損がないと思ったものを選んだ。
※一応テーマ別なので、傑作でもテーマに合わないと判断したものは除外。反対に、テーマに合ったとしても面白いと思わなかったものは除外している。また、1テーマ1作品で選別したため、他のテーマと重複したエピソードはなし。
・大激闘!
5話「電気妖怪の災厄」
12話「首都壊滅! 恐怖の妖怪獣」
28話「妖怪大戦争」
34話「帝王バックベアード」
75話「九尾の狐」
97話「見えてる世界が全てじゃない」
6期はこれまでのシリーズと比べてバトルシーンの簡素化が激しいが、そんな中でもこれは激戦だったなと思ったものをチョイス。カミナリの圧倒的な電気エネルギーを逆手にとって勝利を収めた5話や、まながいなければ間違いなく敗北していた12話。西洋妖怪の圧倒的勢力を痛感することになった28話に、ねずみ男が救世主となった34話も忘れられない。そして、総力戦となった75話も(少々駆け足気味ではあったものの)うまくまとめられていたと思う。
・妖怪が映す社会問題
27話「襲来! バックベアード軍団」(難民問題)
38話「新春食人奇譚火車」(年金不正受給)
47話「赤子さらいの姑獲鳥」(SNSでの印象操作、デマ)
55話「狒々のハラスメント地獄」(ハラスメント問題)
62話「地獄の四将 黒坊主の罠」(改正水道法)
77話「人間消失! 猫仙人の復讐」(多頭飼育崩壊)
79話「こうもり猫のハロウィン大爆発」(渋谷ハロウィン問題)
公害汚染や交通戦争・土地開発など、これまでの鬼太郎も社会問題を根底においた物語が色々とあったが6期も負けてはいない。2019年4月から施行された働き方改革関連法に先駆けて描かれた9話や、水質汚染騒動をもとに改正水道法の懸念事項を描いた62話などは、昨今の政治情勢ネタを取り入れていると言えるだろう。27話や84話における外国と日本の軋轢は双方共に考えるべきものがあるし、「一国家一民族」という思想は既に終わっていることを思い知らされる。47話における印象操作もSNS隆盛の現代ならではの社会問題だ。
・SNSと妖怪
1話「妖怪が目覚めた日」
31話「小豆洗い小豆はかり小豆婆」
44話「なりすましのっぺらぼう」
53話「自己愛暴発! ぬけ首危機一髪」
83話「憎悪の連鎖 妖怪ほうこう」
5期の頃からSNSはあったものの、当時はYou Tube のような動画サイトや2ちゃんねるのような掲示板が主流だったと思う(Twitter は2006年、Facebook は2004年、Instagram は2010年に設立)。それがこの10年ほどで一気に広まり、面白い動画をアップロードしてそこから広告料を得て生計を立てるユーチューバーが職業の一つとして認知されることになったのは注目すべきことであり、一種の発明と呼べるかもしれない。難しい操作なしで自分の意見・知識・技術を世界中に発信できるようになった一方、様々な問題が出てきたのも確かで、6期でもSNS問題を扱った秀作・傑作がいくつもあった。
まず1話で迷惑ユーチューバーが登場し、事件を前に淡々と動画・写真撮影する人々の異様さを描いているのがポイント。1話目からこれが描かれることは即ち6期(2010年台)がSNS隆盛期を表明した訳であり、一億総ジャーナリスト化を示している。それ以降はSNSで存在意義を見失った者(31話)やSNSの「いいね!」機能に振り回される者(67話)、アップロード写真が思わぬ火種となった事件(83話)など、様々な面からSNSの負の側面を描いているが、44話や81話のようにSNSのつながりがプラスになった物語も描いて「SNS=悪」にならないよう公平性を保っている。
・まなと妖怪
3話「たんたん坊の妖怪城」
16話「潮の怪! 海座頭」
29話「狂気のフランケンシュタイン」
49話「名無しと真名」
69話「地獄の四将 鬼童伊吹丸」
3期のユメコちゃん並みの活躍を果たした犬山まなと鬼太郎の出会いは1話から始まるが、友達としての付き合いが始まったのは3話の事件解決後となる。ここから鬼太郎たちとの付き合いが深まり、事件に巻き込まれるのは勿論、時には事件解決のキーウーマンとしてアグレッシブに動いていく点はユメコ以上のものを感じさせる。16話ではまなの先導で鬼太郎メンバーと境港の住人が協力して妖怪退治をする展開が印象に残る。
まなのコミュ力の高さは人間に留まらず、魔女アニエスや伊吹丸も彼女との出会いによって救われることになった。その一方、名無しとの縁によって人間・妖怪間の憎悪を引き起こす道具として利用され、結果的に妖怪が社会に認知された2年目の世界観を作る役割も果たした。
こうなってくると「橋渡し」というより、高速道路や新幹線を開通させるレベルで人間と妖怪をつなげてしまったヒロインと呼ぶ方がふさわしいのかもしれない。
・6期初登場の原作
24話「ねずみ男失踪!? 石妖の罠」
46話「呪いのひな祭 麻桶毛」
65話「建国!? 魔猫の大鳥取帝国」
76話「ぬらりひょんの野望」
4期以降オリジナルエピソードの量産が激しくなり、5期では初めて映像化された原作が出ずじまいだったが、この6期ではアレンジしたエピソードも含めて計8つの原作が初映像化されることになった。そんな中でも24話と76話はほぼ原作通りの展開で視聴者を楽しませ、46話と65話は季節ネタやローカルネタを取り入れた大胆な改変でアっと言わしめた。
・感動作!
6話「厄運のすねこすり」
20話「妖花の記憶」
23話「妖怪アパート秘話」
41話「怪事! 化け草履の乱」
68話「極刑! 地獄流し」
93話「まぼろしの汽車」
3期からだろうか、鬼太郎で思わず泣いてしまうような感動作に出会うようになった。4期が特に感動路線のエピソードが多い印象が強いが、今期もなかなかの感動作揃いだと思う。人によって感動ポイントは違うとはいえ、6話が泣ける名作だという考えは衆目の一致するところのはず。23話や41話の心温まる感動もあれば、68話や93話のように、原作を変えたことで生まれた感動もある。
・仕事と妖怪
40話「終極の譚歌 さら小僧」(お笑い芸人)
43話「永遠の命おどろおどろ」(科学者)
54話「泥田坊と命と大地」(土木業者)
78話「六黒村の魍魎」(カメラマン)
81話「熱血漫画家 妖怪ひでり神」(漫画雑誌編集者)
92話「構成作家は天邪鬼」(TVプロデューサー)
仕事に人生をかける人間はカッコいい一方で危なっかしく、時に一線さえ越えてしまう。その一線の先で出会う妖怪によって吉となったり凶となったりするが、吉となったのは81話と92話くらいで、あとはほとんどが凶の結果。54話は「吉凶相半ばす」と言った所か。
・恋する妖怪たち
10話「消滅! 学校の七不思議」
39話「雪女純白恋愛白書」
63話「恋の七夕妖怪花」
72話「妖怪いやみの色ボケ大作戦」
88話「一反もめんの恋」
人間の闇の深さを描く一方で、恋バナもちゃっかりやっていた6期。一方通行な恋(10話)にすれ違う恋(39話)、見せかけの恋(72話)に純朴な恋(63話)と色とりどりの恋模様が描かれるなかでも、物語全体を通して猫娘の鬼太郎に対するアプローチに変化をもたせた点は評価すべきだと思う。
・ホラーな鬼太郎物語
7話「幽霊電車」
25話「くびれ鬼の呪詛」
45話「真相は万年竹の藪の中」
59話「女妖怪・後神との約束」
70話「霊障 足跡の怪」
86話「鮮血のクリスマス」
バトル漫画として世に出た「ゲゲゲの鬼太郎」も、その原点というべき「墓場鬼太郎」はホラーであり、ホラーな部分に水木作品としての真骨頂があるというのが私なりの意見。基本的に「人間が一番怖い」というのが6期のテイストだが、それだけに頼っていない59話と70話を描いた長谷川氏の脚本力は流石である。7話は社会問題を取り込んだホラー、25話は「着信アリ」のような王道のジャパニーズ・ホラー、45話はミステリ仕立て、86話は外国映画によくある殺戮者に追いかけられる系のホラーと、それぞれにテイストが異なる面白さがある。
・教訓としての妖怪奇譚
4話「不思議の森の禁忌」(自然物の保護)
19話「復活妖怪!? おばけの学校」(学ぶ意味)
22話「暴走!! 最恐妖怪牛鬼」(因習を守ること)
52話「少女失踪! 木の子の森」(親のありがたみ)
64話「水虎が映す心の闇」(復讐の危険性)
71話「唐傘の傘わずらい」(物を大事にすること)
73話「欲望のヤマタノオロチ」(安易に幸福をつかむことの危険性)
80話「陰摩羅鬼の罠」(死者への執着)
水木先生の作品には訓話としての物語が数多くあるが、鬼太郎も例外ではない。22話の牛鬼回は初アニメ化された2期以降ずっと変わらぬテーマを視聴者に投げかけている。19話は夏休み期間中の子供たちに向けたメッセージだと受け止められるし、71話は大量生産・大量消費が当たり前の今だからこそ、改めて考えるべき問題と言えるだろう。
タリホーが選ぶ、オールタイム・ベストエピソード10選!
では、私が選んだオールタイム級のベストエピソードを発表する。
(特に順位はなく放送順で並べました)
1.「厄運のすねこすり」(6話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
「ゲゲゲの鬼太郎」という枠を超えて人々に感動を与える物語として、やはりこれを外すことは出来なかった。人と妖怪の関わることの難しさを過疎化問題を絡ませながら、「ペットと飼い主」という普遍的なモチーフを使って宿命論的悲劇に仕立て上げた物語。ある種テンプレ的なプロットではあるが、「好きな人と一緒にいられない苦しみ・悲しみ」を背負うすねこすりの姿に、胸がつまる。
2.「まくら返しと幻の夢」(14話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
約20分という尺の中に、親子の絆・意外な展開・敵の背景・仄かな苦みを残す結末など様々な事象が詰め込まれたにもかかわらずまとまっており、物語の構成のクオリティの高さが凄いと感じた回。コミカルな展開の中にも人間のプラスの面(人を救済する心・強い絆)とマイナスの面(他者を見捨てる心・生贄)が描かれており、息子のため逞しくあろうとする父親と生贄の犠牲になった少女は別個ではなくどちらもプラスになりマイナスとなる表裏一体の存在なのだ。目玉おやじが意外な姿となって登場したのも、そういった二面性の表れなのかもしれない。
3.「帝王バックベアード」(34話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
単純にバトルものとして熱い回と評価しても良いが、「どっちを取るか」という善悪二元論で物事を判断しようとする愚かさや、それを克服しようとする鬼太郎のヒーローとしてのカッコよさが描かれているのが素晴らしい。日本に火の粉を持ち込んだアニエスやヘイトスピーチによる扇動を行ったねずみ男は「小悪」と呼べる存在だが、彼らは小悪とならざるを得なかった存在であり、そんな小悪を救うために巨悪のバックベアードを倒そうとする鬼太郎にグッとくる。正直、地獄の四将編みたいにゴチャゴチャ石動と己の正義感を言い合っている場面よりずっと明確で、誠実さを感じる。
4.「終極の譚歌 さら小僧」(40話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
「芸のためなら女房も泣かす」と浪花恋しぐれにあるが、幸福への道は何も平和の先にあるとは限らないという法律や道徳観、善悪を超越した先の幸福を求めてしまった男の話。刑務所で一生を過ごしたいがために人を殺すやつが現実にいるのだから、自分の身を破滅させて幸福を掴むやつがいてもおかしくない。子供向けアニメでありながら社会的に許されない幸福の一形態を描いた回として後世に残すべきだろう。
5.「泥田坊と命と大地」(54話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
「帝王バックベアード」と同様、これまで善悪二元論で描かれていたアニメにおける泥田坊回を「そんな単純に割り切れるものではない」話として見事にアレンジさせた回。泥田坊も人間も双方共に正しいところがある一方間違っている(或いは良くない)ところもあるように描かれており、元ある土地を別の姿に変える人間が悪いのか、土地の在り方に固執して人命を奪う妖怪が悪いのか、その裁定に懊悩する鬼太郎が印象深い。「裁き」と「多様性の尊重」は相容れ難きものという、令和初の鬼太郎物語に相応しいプロットとなった。
6.「魅惑の旋律 吸血鬼エリート」(56話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
原作やこれまでのアニメになかった吸血鬼エリートの歴史を描いたことで、4期とはまた別の哀愁が漂うエリートが生まれた、という点でこの回をチョイス。支配者への羨望と憎悪、そして革命行為により支配者側へまわって以降は革命行為を受けぬよう陰から支配するというエリートの行動原理の深掘りがなされたと同時に、ダモクレスの剣的なオチによって(支配階級が)逃れられない失墜の運命が描かれているのもポイント。ねずみ男が“持たざる者=失うものがない者”として対比的な位置にいることで、よりその運命の絶対性が強調されていた気がする。
7.「妖怪いやみの色ボケ大作戦」(72話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
これまでのお下劣である種キワモノ的な描かれ方をされてきたいやみ回をラブコメに変えてしまった革新的な脚本。楽しみを吸い取るいやみの設定をカットし、偽りのラブを振りまき色ボケ状態にする設定一本で通した潔さがプラスになった。脚本もさることながら、猫娘の心象風景の演出がまた良いアクセントになっている。
8.「ぬらりひょんの野望」(76話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
悪しき昭和性を体現した妖怪という、3期以降のぬらりひょん像を一新した脚本に天晴。政治力と資金力を武器にして人と妖怪の二者を操るなど、6期の社会派的な一面に相応しいラスボスとして絶大なインパクトを残した。その幕開けとなったこの回を私は推していきたい。
9.「六黒村の魍魎」(78話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
アニメというより一つの文学作品を読んだかのような余韻を残すのがこの魍魎回。芥川龍之介の「地獄変」や京極夏彦の『魍魎の匣』のような、人としての一線を越えた先にあるものを描き、第三者には理解しがたい愛を表現した奥深さ。亡霊という直接的なホラーと人間の業というホラーの組み合わせ。どれを取っても申し分なし。
10.「まぼろしの汽車」(93話)
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
吉野氏の1話完結ものの脚本力の高さを改めて知った回。20分でタイムループものをやってのけたことも凄いが、2話から少しずつ描かれてきた猫娘の鬼太郎に対する恋情の一到達点を描いた回として後々語られることになるだろう。そしてこの回で描かれた運命の是非が未来に託されているという点で非常に重要な回でもある。
タリホー考案、「あったら良いな、こんな鬼太郎物語」
「自分だったら6期の世界観でもっと面白い話が書けるぞ!」と思った鬼太郎ファンもいただろうし、ほかならぬ私がそうなのだが、折角なので私が考案した6期の世界観に相応しい鬼太郎物語をご紹介しよう。(勿論、妄想なので放送されませんよ!)
「激憤! 妖怪大首」
富士登山客が次々と死亡する謎のポックリ病が蔓延。調査に乗り出した鬼太郎たちは、特に外国人登山客の死亡数が多いことに疑問を抱く。その頃、富士の胎内洞窟では眠りから覚めた妖怪・大首が怒り狂っていた。「よくも聖地を汚しおって!!」。大首の怒りの理由は? そして連続するポックリ病は何故起こったのか?
(昨年「ザワつく! 一茂良純時々ちさ子の会」というバラエティ番組で外国人登山客のマナー問題が取り沙汰されていたのを見て「これと原作の大首ネタと合わせてやったら6期らしい話になりそう」と思っていた)
「蝋人形の街」
まなの近所にマリーというフランス人女性が引っ越して来た。マリーから「お近づきの印に」とフランス産の人形をもらったまなは、その人形が言葉をしゃべることに気づく。数日後、その人形はまなの父が行方知れずになることを予言し、その通りになってしまう。鬼太郎と猫娘はまなの父を探すためにまなの元へ向かうが、ちょうどその時、父が帰って来た。時刻は夕方、5時を知らせるサイレンが街中に鳴り響いていた時のことだ。特にケガもなく無事に帰ってきたことに鬼太郎たちは安心したが、それからしばらく経ったある日、まなと連絡が取れなくなる。猫娘は異変に気付いて家に向かうが、まなの家だけでなく街全体がひっそりと静まりかえっていることに違和感を覚えて…。
(以前から私はずーっと原作の「おばけ旅行編」のエピソードをアニメ化してほしいと思っており、その中でもカリーカの話は絶対にやるべきだと言いたい。この原作ならアニメ「学校の怪談」のうつしみ回のようなホラーが演出出来るからだ。ポイントは夕方5時に鳴り響くサイレンで、これが原作のアレと同じ効果を発揮する)
「聖夜の毛羽毛現」
恐竜好きの小学生・五平の夢は、恐竜の背中に乗ること。しかし同級生からは「恐竜は絶滅したから絶対に無理だ」と笑われる始末。それでも夢を捨てられない五平は、もうすぐクリスマスということもあって、サンタさんにその夢が叶うよう祈っていた。その頃、鬼太郎は街で連続している子供の失踪事件を追っていた。子供が消えたのは決まって夜であり、しかも「大きなニワトリに乗ったサンタクロースが子供をさらった」という目撃証言も出てきて…?
(86話のクリスマス回の放送前に、ゲスト妖怪が毛羽毛現と予測していた方を見かけたが、サンタクロースとの組み合わせという点では夜叉より毛羽毛現の方が個人的にはしっくり来ていると思うし、子供の魂を使って恐竜を復活させる原作のプロットを活かせば感動作としての効果を上げられるだろう)
「百花繚乱 ラグレシアの園」
調布の神代植物公園に、南方から世界最大級のラフレシアの花が持ち込まれた。しかしその正体は吸血花ラグレシアであり、バックベアード復活の生き血を集めるためカミーラによって送り込まれたのだ。大温室で大きく成長したラグレシアは不思議な音楽を奏でて人々を眠らせ、次々と生き血を回収していく。一方その頃、まなのことが忘れられずにいたヴィクター・フランケンシュタインは、密かに猛毒入りのケーキを作って彼女に食べさせようとしていた…。
(基本的に鬼太郎作品に出て来る妖怪は色味が悪いので、文字通り華のあるラグレシアを推していきたい。バックベアードの復活計画が描かれたとはいえ、実質2,3話程度と少なかったので、西洋妖怪で特に出番が少ないフランケンにスポットを当ててやりたいという思いを込めて、『国盗り物語』の毒娘に相当する役目をまなに負わせることにした)
「めんこ天狗とあまめはぎ」
めんこの面白さを世に伝えるべく100年間修業を続けていためんこ天狗は、その間にめんこが廃れTVゲームが流行していることに絶望する。それを見かねたコマ妖怪のあまめはぎは彼をゲゲゲの森へと誘う。妖怪の間でめんこが流行り、何とか慰めを得ためんこ天狗だったが、そんな折香川県でゲーム規制条例が成立したことを耳にして「香川でめんこの面白さを広めてやる!」と意気込んで香川に向かうが…。
(超タイムリーな時事ネタを入れられるのならば、やはりゲーム規制条例とめんこ天狗を掛け合わせてみたい。そこに、特定の玩具に造詣が深く、時代に対応出来ないことが元で過去に鬼太郎と闘ったあまめはぎが加われば、物語がより多層的になるのではないだろうか?)
「馬狂い! 馬魔の陰謀」
競馬場でレース中に競走馬が急死する事件が相次いで起こった。目玉おやじは馬を殺す妖怪・馬魔(ぎば)の仕業ではないかと疑うが、競馬場だけで連続して起こることがどうしても腑に落ちない。しかし、猫娘は競馬場という場所柄「アイツ」が絡んでいるのではないかと思い彼を密偵する。
(もしアニメオリジナル脚本を書くとしたら馬魔をメインにする。猫娘のいう「アイツ」とは勿論ねずみ男で、馬魔と組んで自分が賭けた馬が一等になって当たるように他の馬を殺させていたという真相が出て来るのだけど、これで話は終わらない。実は馬魔はねずみ男だけでなく死神とも手を組んでおり、死神は競走馬の急死によって落馬したり、振り落とされて他の馬に轢かれて死んだ騎手の魂を集めることを画策していた、という具合に二段構えの構成でいきたい。死神を取り入れたアイデアは「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」を基にした)
「髪様の布教大戦」
地の果てのような沖の島で信仰の対象として崇められていた髪様は、島の過疎化と高齢化によってその信仰が廃れてしまったことを憂いていた。新たな信仰者開拓のために本州へ毛目玉と共に渡るものの布教はうまくいかず、遂に髪様は強硬手段として人々の髪の毛を奪う行為に走ってしまう!街で起こった髪の毛パニックは自衛隊まで出動する騒ぎとなるが、この騒動を見て一人笑う女の子がいた。
(この現代において原作通り生贄を要求するプロットはそぐわないので、信仰が廃れた島から本州へ渡り布教のため奮闘するプロットとした。この笑う女の子というのは病気で髪の毛を失った子供であり、髪の毛を失ったショックで塞ぎ込んでいたという設定にした。これによって「何が人にとって災いとなったり救いになるのかわからない」というテーマ性が出て来るのでは…と思っている)



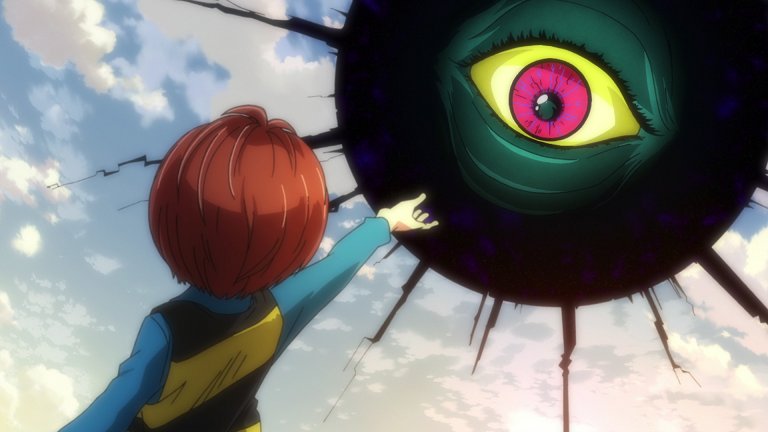



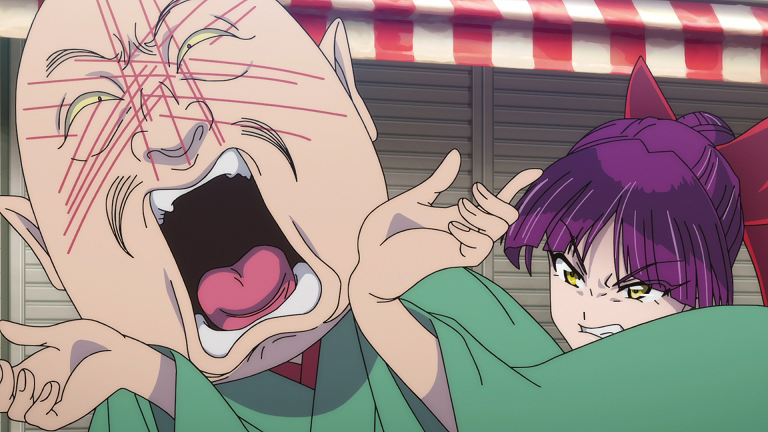








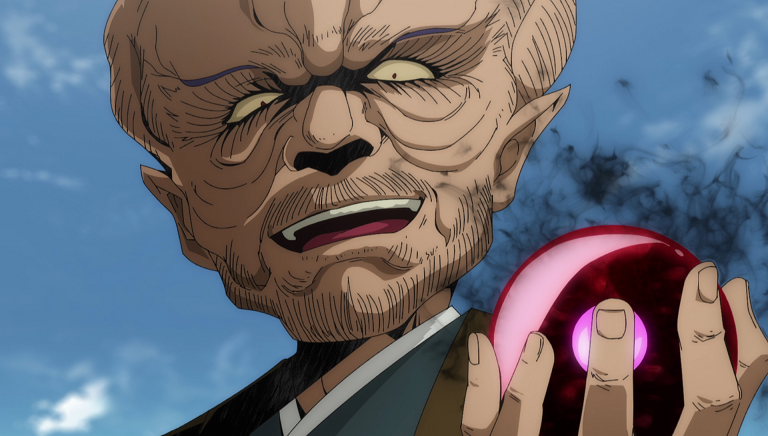

![クリスタル殺人事件 デジタル・リマスター版 [DVD] クリスタル殺人事件 デジタル・リマスター版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51m8kuWXNlL.jpg)


