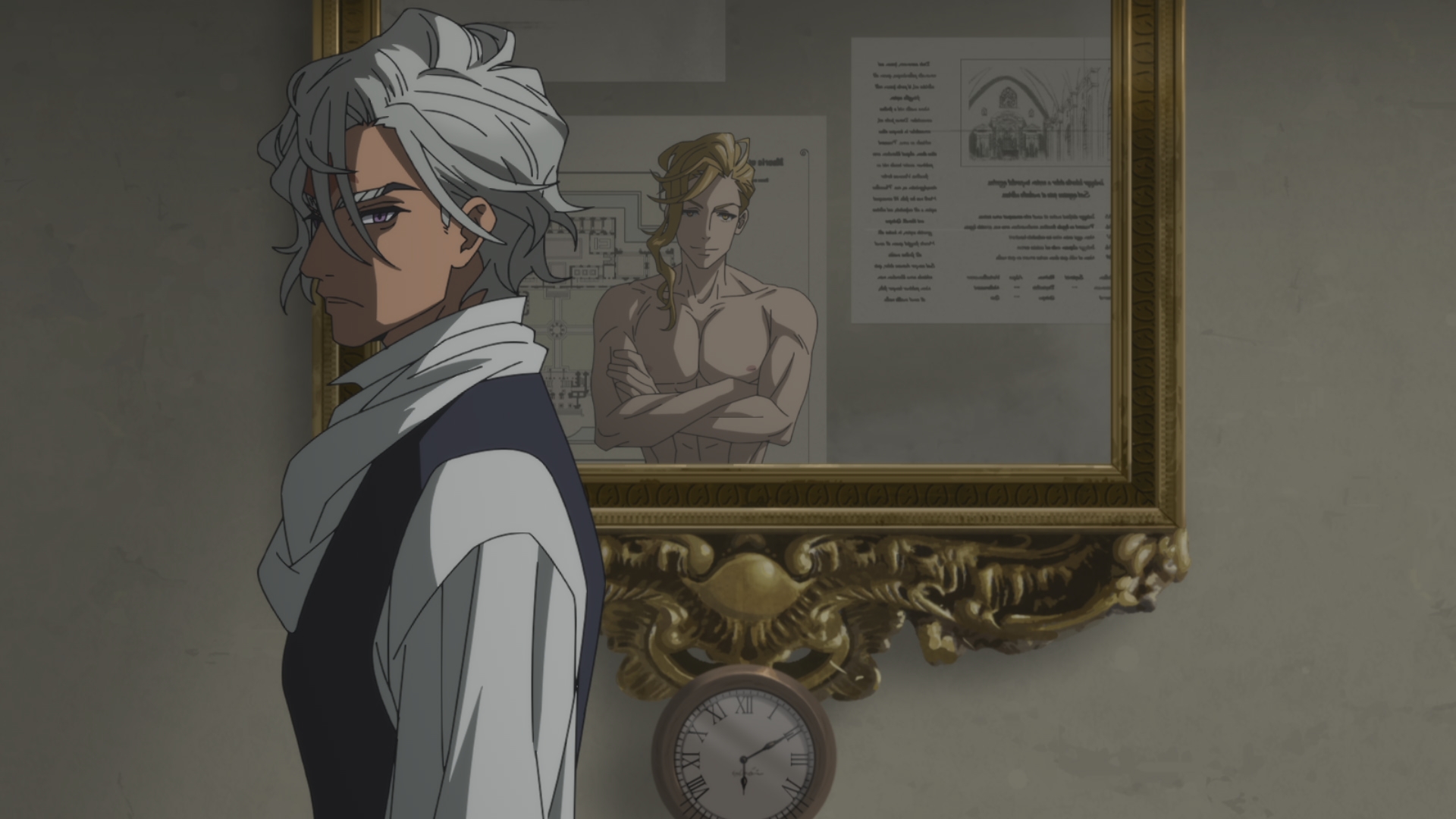© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
ロンドンを舞台にした第二章「ダイヤ争奪」編の始まりです!
第二章のPV(↓)を見たけど、原作の内容を知っていても豪華さに圧倒されるというか「え、これ劇場版予告じゃないの?」って思いましたよ。ワクワクが止まらない。
「倫敦の不死者」
今回から始まる第二章は原作2巻のエピソード。ご承知の通りこのエピソードでは世界にその名をとどろかす名探偵シャーロック・ホームズと相棒のワトソン、フランスの怪盗紳士アルセーヌ・ルパンにオペラ座の怪人ファントムといった19世紀後半から20世紀初頭にかけて発表された海外古典文学の有名人が一堂に会し、ブラックダイヤモンド〈最後から二番目の夜〉を巡って熾烈な争奪戦を繰り広げる。
そんな訳で、ルパンやホームズといった原典を読んだことがない人にとっては「何か凄い名探偵と怪盗(+怪人)がお宝を巡ってバトルするんでしょ?」という感じで把握しているだろうし別にその程度の認識でも十分に面白い作品なのだが、当ブログはミステリを深く語ることをモットーとしているので、「原典を読んだことがないそこのあなたも最低限これくらいは知っておいてね?」という思いで彼らの情報をお届けしたい。特にルパンなんて三世の方が有名でじっちゃんにあたるアルセーヌの方はアニメ好きの人は知らなさそうだし、実は私もあまり詳しくないから先月ルパンとホームズの短編集を買って予習したんだけどね…。
アンファル放送前に、ホームズの『回想』とルパンの短編集を一冊ずつ買った。流石に原典に目を通さず見るのはミステリマニアとして忍びなく感じたので。 pic.twitter.com/v2Mh0qy9ML
— タリホー@ホンミス島 (@sshorii10281) 2023年7月1日
舞台となる19世紀末のロンドンは原作でも記されている通り、中心街の西側(ウエストエンド)は政治的・文化的に発展した裕福な街なのに対し、東側(イーストエンド)は種々雑多な移民や貧しい労働者・娼婦といった人々が暮らす貧民街となっている。特にイーストエンドのホワイトチャペル通りは、1888年に切り裂きジャックによる連続殺人事件が起こった場所として現在でもツアーの観光名所になっている。
そんな都市の光と闇の両面を有するロンドンのウエストエンド、テムズ川沿いにあるフィリアス・フォッグ邸が今回の物語のメインの舞台となる屋敷だが、このフィリアス・フォッグなる大富豪もホームズと同じく海外古典の有名人の一人で、ジュール・ヴェルヌが1872年に発表した『八十日間世界一周』に登場する。
ヴェルヌの小説は『十五少年漂流記』は読んだことがあるけど『八十日間~』は読んだことがないのでWikipediaの記事を引用するが、内容を見た感じ大人向けの冒険小説といった感じで、原作のフォッグ氏は賭けには勝ったものの財産のほどんどを旅行に費やし、旅先で救い出した女性が唯一にして最高の収穫だったという形で物語を終えている。
一方こちらのアンファルの世界のフォッグ氏はその冒険譚が話題となって富と名声が舞い込み、総資産200万ポンド超えの大富豪となったようで、現在は屋敷を住居兼私設博物館として開放している…という設定だ。
アルセーヌ・ルパンについて
/
— TVアニメ『アンデッドガール・マーダーファルス』公式 (@undeadgirl_PR) 2023年8月2日
第5話「倫敦の不死者」
📣本日24:55~放送スタート
\
ロンドンのフォッグの元に、怪盗ルパンから人工ダイヤ<最後から二番目の夜>を狙うと予告状が届き、世界最高の探偵シャーロック・ホームズと<鳥籠使い>一行に依頼が舞い込む...。
📺放送・配信情報https://t.co/AXy9d3gpie#アンファル pic.twitter.com/pMVf5JOpOF
5話は原作の最初(第0節)から77頁(第5節)までの内容。ルパンとファントムの出会い、ホームズ&ワトソンと〈鳥籠使い〉の出会い、そしてダイヤと保管場所に関する情報、大手保険機構「ロイス」(原作は実在の企業名と同じロイズ)に教授率いる〈夜宴〉の存在といった具合に、第二章における登場人物と物語の基本となる情報をおさえた回になる。流石に今回は全部の登場人物について言及していたらキリがないので、今回はルパンとホームズについて言及していこう。
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
まずはルパンについて。原作は小説家モーリス・ルブランが編集者のピエール・ラフィットからの依頼で行動小説(アクション小説)を書き、それがルパンシリーズの始まりとして1905年7月号の「ジュ・セ・トゥー」誌に掲載される。当初ルブランはシリーズものとして書いたつもりはなく、最初の短編を読んだラフィットが当時既に人気を博していたホームズシリーズに匹敵するとルブランを説得し、以後ルブランはルパンシリーズに専念することになるが、高尚な心理小説から大衆向けの文学作品へと作風を移行することに対してはホームズを生み出したコナン・ドイルと同様に、やはり忸怩たる思いがあったらしい。作者が仕方なく生み出したキャラが海外古典ミステリの二大巨頭として後に君臨することになるのだから、全く皮肉な話である。
そんなルパンが初めて登場する舞台はアメリカに向けて航行中の客船。船内にルパンが偽名を使って潜んでいるという電報が届き、船内は大混乱。宝石が盗まれたり乗客の一人が襲われて、さぁ誰がルパンなのか?という感じで話が進んでいくのだが、えーとこれタイトルが直球でネタバレというか、デビュー作のタイトルはずばり「アルセーヌ・リュパンの逮捕」。そう、デビュー作にしていきなり逮捕されちゃうんですよルパン。まぁこれはルブランが当初からシリーズ化するつもりがなかったからであり、ラフィットが「捕まったのなら脱獄させれば良い」と言って「獄中のアルセーヌ・リュパン」「アルセーヌ・リュパンの脱走」という具合に話を続けさせていったのだが、このルパンシリーズの面白い所はルパンが怪盗としてだけでなく探偵としても活動する時期があり、特に『八点鐘』はミステリとして優れた短編集としてエラリー・クイーンといったミステリ作家からも高く評価されている。
ルパンがホームズと人気を二分したというのはホームズと同様に変装の達人であり名探偵としての知性があることや、日本の武術(ルパンは柔道、ホームズはバリツ)を習得しているといった共通項から見出すことが出来るが、ホームズにはないルパンの魅力は何かと問われると私は彼のディレッタント(風流人)としての振る舞いや行動原理にそれがあると考えている。
〈リュパンは泥棒ではあるが、同時にディレッタント(風流人)でもあったのだ。彼はなるほど趣味と天職とによって仕事をしていたが、しかしまた、それは娯楽でもあった。まるで、自分の作品を上演させて、舞台裏で自分の才気や、創作した場面などを、大笑いしている紳士の観があった。〉
「これがアルセーヌ・リュパンだとは、だれにも断言できないのは結構ですよ。大事なことは、それをしたのはアルセーヌ・リュパンだと、まちがいの心配なしに言えることなのです」
「アルセーヌ・リュパンの逮捕」より
デビュー作から既にルパンはこのような人物として描写されており、彼が怪盗として活動することになったルーツも短編集『怪盗紳士リュパン』の中の一作で明かされている。あいにくだがその作品を明かすと作中のトリックのネタバレになってしまうのでオブラートに包んで言及すると、ルパンは体育教師の父と貴族階級の母との間に生まれた子で、父親はとある犯罪で捕まり獄死、母親は知り合いの伯爵夫人を頼って居候となるが使用人同然の扱いを受けるといった始末で、なかなか辛い幼少期であったことが作中からうかがえる。彼が怪盗紳士として貴族や富豪が所有する宝石や美術品を狙うのは、以上のような幼少期に味わった経験がベースとなっていると考えられるし、怪盗紳士として行動する上で父親ゆずりの肉体と母親ゆずりの知性・品格がそれを支えていたというキャラ設定も実に魅力的だなと思っている。
そして、彼の活動はこの世界を大きな劇場に見立てて、世界中の人々を役者の一人として自分のプロデュースした世界の中に立たせるという面もあり、ルパンにかかれば普段は観客として劇場に来る側の上流階級の人々も、舞台上の喜劇俳優のように操られ翻弄されてしまう。ある意味ではこれが母と自分を虐げた者たちに対するルパンなりの復讐になっていると読み解くことが出来よう。そういう点では、ルパンは真打津軽と発想の面では似通った所があるのかもしれない。津軽も1話において下衆で低俗な観客を金網の向こうで繰り広げられる殺し合いの見世物の側に引きずり込むことを目的としていたのだからね。サニーサイドかダークサイドか違うってだけで根っこは同じという感じだ。
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
本作ではルパンがオペラ座の怪人を相棒として「盗み出す」という始まりになっているが、本来ならファントムは原作通りその生涯をオペラ座で過ごし死ぬことになる存在だ。それを劇場の外に引きずり出して盗難計画の相棒にするという発想自体が面白いし、ファントムの能力――投げ縄と奇術の達人――を買って仲間として引き入れたことは間違いない。でも私はそれに加えて先ほど述べたルパンの価値観、つまりこの世界そのものが大きな劇場であるということをファントムにも知ってもらいたかった。オペラ座という小さな劇場でなくともこの世界をプロデュース出来るというルパンなりの美学に基づいてファントムを啓蒙しようという試みである。
ちなみに、フォッグ邸の事件が起こった1899年当時のルパンは25歳の青年であり、ルブランの原作に基づくならこの後ガニマール警部に逮捕されることになるはずだ。それと、冒頭でルパンが言っていた「エギュイ・クルーズ(空洞の針)」はアニメでは船上を示しているが、原作は船ではない。これに関してはネタバレになるので詳しくは長編『奇巌城』を読んでいただきたい。
シャーロック・ホームズについて
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
ホームズについては(個人的に)ルパンと比べるとかなり有名だと思っているし、今現在においてもホームズとワトソンは名探偵とその助手を示す代名詞として用いられている。多くの作家や脚本家が未だにこの王道とも言える設定・プロットをこすり続けているのだから、もう簡単に紹介して終わろうかと思ったが一応ルパンと同じくらいの内容は紹介しておこう。
シャーロック・ホームズは1886年に長編『緋色の研究』で初登場。以後、短編・長編合わせて60の作品に登場するが発表当初から人気があった訳ではなく、人気が出たのはストランド・マガジンに発刊されることになった1891年の短編「ボヘミアの醜聞」以降のことである。一躍ホームズ譚が人気になったとはいえ、ルブランと同様ドイルは歴史小説の方で名を残したいと思っており、1893年の「最後の事件」でホームズをライヘンバッハの滝に落として死なせるという手段をとった。
しかし、1901年に友人から聞いた魔犬伝説を元にした『バスカヴィル家の犬』を書き、読者の復活要望の声に応えて1903年に「空き家の冒険」でホームズを完全復活させた。復活以降は1927年までホームズ譚を書いているが、この頃のドイルは心霊主義に傾倒していたこともあって、作品としては精彩を欠いているという批判があったそうである。
さて、シャーロック・ホームズと言えば卓越した推理力が印象的で、一目会っただけでその人が過去にどこに行ってどんな生活をして、今何に困っているのかといった事柄を瞬時に見抜いてしまう場面が見受けられるが、彼の推理力は犯罪に関わる植物や地質学といった特定の学問分野に対する造詣の深さと、彼がコールド・リーディングの達人であるというこの二点によって支えられていると私は考えている。
コールド・リーディングは相手の外見や話などからその人のことを読み取る技法で、よく手品師や占い師などが用いる技法だ。これは一般的な心理学と違い体系的に分類出来ない技法で、例えば「腕時計を右腕につけているからその人は左利きである」ということは大抵はそうかもしれないが100%そうだと言えないので、ある程度は読み取る人自身のセンスや経験・勘の鋭さによってコールド・リーディングはその精度が左右されると思う。ホームズはその辺りの精度がずば抜けているという点で達人であり、だからこそ名探偵として名を馳せることが出来たのだ。彼の探偵としての手法は今現在における科学捜査やプロファイリングにも通ずるので、そういった犯罪捜査の先駆けをやっているのも当時の読者の興味を引いたに違いない。
ただ、ホームズの探偵としての能力は武器であると同時に弱点でもあるというのが私の思う所で、今言ったずば抜けたコールド・リーディングの能力も、例えば犯人が意図的にホームズを騙そうと服装や身体のクセ・所持品などを別の誰かに完璧に偽装したら恐らくホームズも見抜くことは困難になるだろう。ホームズは突発的な事件(=犯人側が探偵が来ることを予期していない)には強い一方で、犯人側が探偵が調査に来ることを見越していた場合においては、その鋭さを逆手に取られる危険もあるという弱点を抱えた探偵なのだ。そう考えると今回のルパンとの対決、ホームズにとっては分が悪い対決になるんじゃないの~?と思うかもしれないが、その対決の行方は是非次回以降を楽しみにしてもらいたい。
ところで、ホームズが何故発表当時多くの読者の心をつかんだのかと私なりに考えてみたことがあって、それは勿論物語自体が面白いということや、ストランド・マガジンに掲載された際のシドニー・パジェットによる挿絵がキャラの印象を固めたことも貢献しているとは思うが、それだけではなくホームズが作中で示したように観察と推理を使えば誰でも相手を見抜けるというこの部分に読者の心を動かすポイントがあったのではないかと考えている。
ここからは私の勝手な想像に過ぎないが、ホームズを読む前の一般の読者にとって日常生活というのは至って凡庸であり、周りにいる人々も労働者・中年の婦人という記号として配置されたような人物に見えていただろう。特に都市部では顔見知りよりも赤の他人の方が圧倒的に多いのだから、行きかう人々は記号的存在という見方しか出来なかった人も多いのではないだろうか。
しかし、ホームズの物語を読めば、一見なんてことのない紳士や婦人からもその人の過去や今の暮らしぶりなどが読み取れるということが示されているのだから、当時それを読んだ人々は少なからずホームズの真似事をして周囲の人を観察してみようと思ったはずだ。ホームズがもたらした見識は、これまで記号にしか過ぎなかった自分以外の周囲の人々にもドラマがあることを読者に教えてくれた。これまで受動的に雑誌や本、新聞で物語や実録ドラマを追うだけでは味わえなかった、自ら物語を掘り出し見出すことの面白さを我々読者に与えたという点でも、ホームズが与えた影響はミステリの枠組みだけで語れないと言えるだろう。
余談になるが、1899年当時のホームズは45歳、ワトソンの年齢は1878年に医学博士号を取得したことから50歳前後と推測される。アニメでは描かれなかったが、原作では顧客リストを盗み出した津軽を見咎め二人がかりで戦闘、彼らが中高年だと考えると半人半鬼の怪物相手に健闘していたことに驚くばかりだ。
さいごに
ということで、二章の始まりとなる5話はルパンとホームズの基礎知識とその魅力について語ったが、今回紹介したのはあくまでも基礎知識なのでネットで探せばもっと詳しいサイトが見つかるだろうし、原典は青空文庫でも読めるので是非本作でホームズとルパンが気になった方は調べてその魅力に触れてもらいたい。
ちなみに、ルブランは1908年に『ルパン対ホームズ』という作品集を発表しており、ルパンとホームズを自作内で戦わせている。ただ、ホームズの名を作者のドイルに無断で借用して抗議を受けたため、後にエルロック・ショルメという名に変更している。
(ただし、ルブランもドイルもその件について明確な証言を残していないので真偽のほどは定かではない。名前の変更は事実だけどね)
さて、これだけ有名人が一堂に会したら原作未読の方がやはり気になるのは物語をどう着地させるのかという点だろう。ホームズにしろルパンにしろどちらか片方を依怙贔屓するような結末にしたら一方の側が「許さん!」ってことになるし、かと言って本作の主人公〈鳥籠使い〉一行に華を持たせる結末にしたら海外古典の有名人を引き立て役に利用したみたいで往年のファンにとっては気分が悪いだろう。それに保険機構ロイスの存在や〈夜宴〉の介入も間違いなくあるだろうから、果たして原作者の青崎氏は自身が作り上げたこの設定・世界観をどういう結末に持ち込むのか、それが最大の見所となる。
ミステリとしては、もう既に提示されている通りルパンがいかにして宝石ならびに金庫を盗み出すのか、その手段(ハウダニット)が問われている。この手段に関しては大きく分けて三つの困難があり、「①侵入の困難」「②盗難の困難」「③脱出の困難」の三点をクリアしないといけない。フォッグ邸に入れてもダイヤと金庫をゲット出来なければ意味がないし、ゲット出来た所で脱出出来なければ捕まってしまう。この三点をクリア出来るスマートな解決策があるのか、そこも注目ポイントだ。
そしてもう一つの謎はダイヤに刻まれた詩の意味。人狼に滅ぼされたドワーフ族が追い詰められた際、復讐のため人狼の隠れ里を示すヒントをこのダイヤに残したと言われているが、この詩が示すものとは何か?ちょっとした暗号解読として考えてみるのも面白いかもしれない。