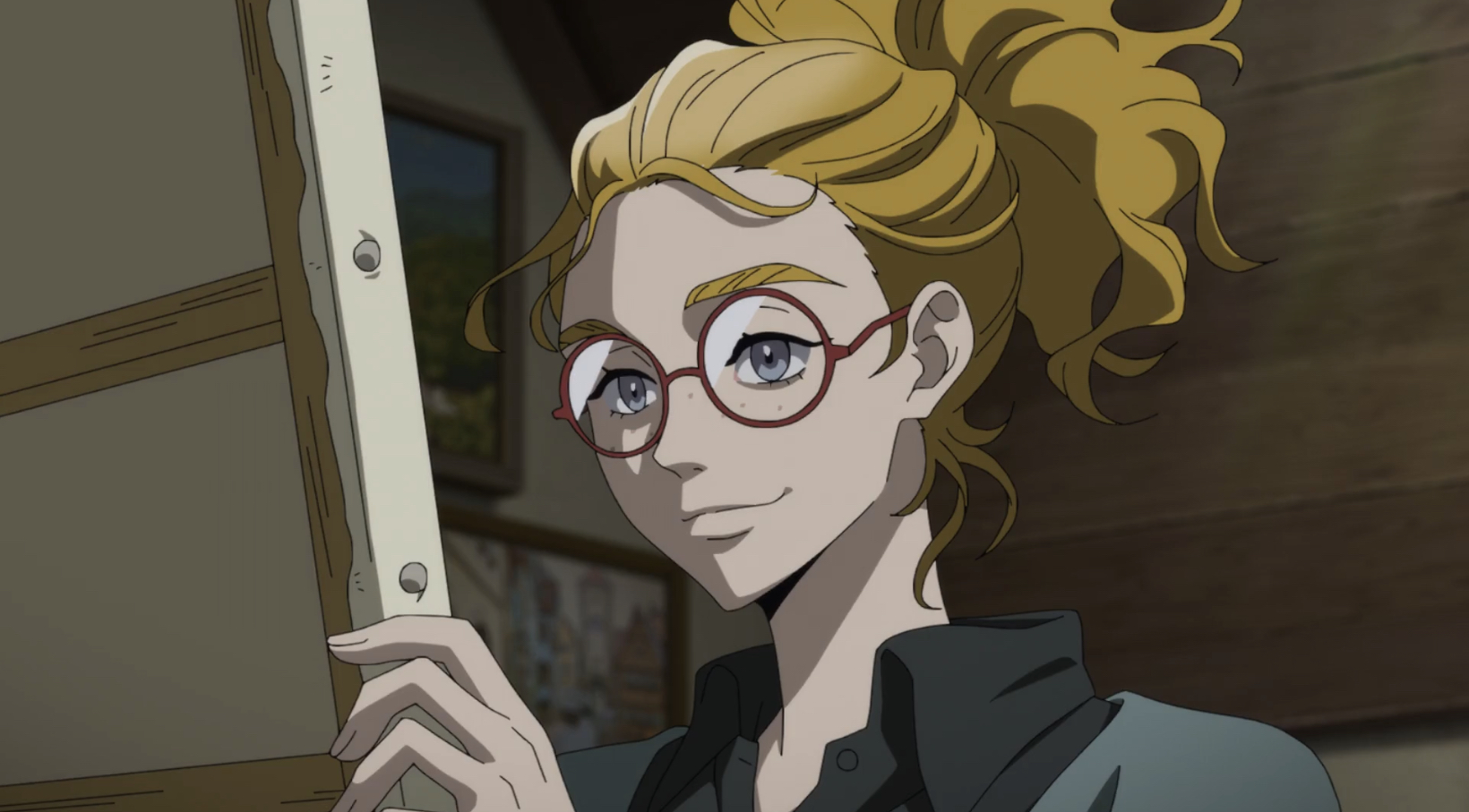「アオサキ夏のミステリまつり」と題して7月から追っていたドラマ「ノッキンオン・ロックドドア」が先日最終回を迎え、そしてアンファルも最終回を迎えました。
青崎有吾氏の作品が同クールに二作品も映像化されるというミステリオタには夢のような三ヶ月でしたが、それも今日で終わり。名残惜しいけど最後なので徹底的に感想・解説を語っていきますよ!
あ、そうそう今回は人狼編の最終回でもあるので、「狼」つながりでこちらの曲をご紹介。
事件の真相を踏まえて聞くと、より一層深みが出る曲ですよね。
(この曲は昔NHKでやっていたアニメ「アリスSOS」で知りました)
(以下、原作を含めた事件のネタバレあり)
「犯人の名前」
/
— TVアニメ『アンデッドガール・マーダーファルス』公式 (@undeadgirl_PR) 2023年9月27日
第13話(最終話)「犯人の名前」
📣本日24:50~放送スタート
※いつもより5分早い放送になります。
\
鴉夜はヴォルフィンヘーレとホイレンドルフの村人たちを集め、2つの事件の謎解きを始める―――。
📺放送・配信情報https://t.co/AXy9d3gpie#アンファル pic.twitter.com/8By3HOoisR
最終回は原作の361頁から460頁(第26節「怪物のとりえ」から第31節「夜明け前の怪物たち」)までの内容。序盤の5分間で静句とカーミラ、クロウリーとアリス、カイルとヴィクター(+津軽)の三つの戦いを描き、残り時間で二つの村で起こった連続少女殺害事件の謎解きをするという1秒とて無駄に出来ない構成を何とか20分ほどの尺で収めている。そんな訳でクロウリーに負けたアリスがどうなったのか、〈夜宴〉は当初の予定通りサンプルとなる人狼を確保出来たのか、といった細かい部分はカットされている。気になる方は是非原作を読んでもらいたい。
ちなみに今回の静句対カーミラの戦いは原作通りやるとR18でいくら深夜アニメでもエロ過ぎるので、婉曲的な表現で演出しているとのこと。
原作どおりだと静句さんが放送できない目にあうので婉曲表現になったよ #アンファル
— 青崎有吾 (@AosakiYugo) 2023年9月27日
事件解説(二種類の一人二役)
原作でもアニメでも8年前のローザとユッテ母子の焼き討ち事件が回想として挿入されていたので、今回の事件が生き残ったユッテの仕業だというのは推理しなくとも何となくわかることだし、特にアニメではユッテとルイーゼが似ている※1のは一目瞭然なので、ノラ(=ユッテ)の一人二役トリックに気づいた方は多いのではないだろうか?
一人二役トリックの最初の手がかりとして視聴者(読者)に提示されたのは、鴉夜が何度も言及したルイーゼ誘拐現場で割られた窓。人狼がそこから脱出したのは間違いないとして、どの形態で脱出したのかが問題となるが、【獣人】だと体格が大きすぎて窓枠から身体を出せないし、【人間】だと窓枠の下辺が大人のへその高さにあるためまたぎ越すのが困難。加えて窓枠にはガラス片が付いていたので仮にそこから【人間】として何とか脱出出来たとしても、ルイーゼの声を聞いて部屋に入ったグスタフに姿が目撃されていないとおかしいのだ。※2
ということで人狼は四足歩行の【狼】の姿で脱出したことになるが、そうなると狼の姿で12歳の少女を連れ去ったという不可能状況が生じる。少女を口にくわえて窓からは出せないし、引きずり出したら窓枠下辺のガラス片が全部外に落ちていないとおかしい。つまりルイーゼは部屋から出ておらず、人狼だけが部屋から出た。しかも侵入口と思しき暖炉には灰が飛び散った痕跡がないため、そもそも最初から部屋に人狼がいたことになる。
以上の推理から鴉夜は人狼はルイーゼに化けており本物のルイーゼと入れ替わっていたこと、誘拐事件は偽ルイーゼの自作自演と見抜いたが、現場検証の段階でそれを見抜きながらグスタフや村人たちにそれを語らなかったという点については後ほど言及する。
そしてホイレンドルフとヴォルフィンヘーレの二つの村で起こった少女連続殺害事件に移るが、この事件では4ヶ月周期・雨の夜・10代前半の少女といった規則性のある犯行が最大の謎であり、何故かノラとルイーゼの事件だけこれまでの法則と違う犯行だというのも引っかかるポイントだ。
その答えはもう既に原作と今回の物語を見た方ならご存じの通り、人狼村の少女を村から逃がすためであり、ノラの一人二役だけでなく死体の一人二役というトリックが盛り込まれているのがミステリとして面白いポイント。よく考えれば人狼村の被害者たちが全員真正面から顔を撃たれていたということ自体が不自然で、人狼なら五感の鋭さで相手の気配や居場所がわかるし、正面から銃を構えている者がいるならばすぐに【獣人】か【狼】に変化すれば毛皮の防御で少なくとも死ぬことはないのだから、その状態にならずに死んでいたということ自体、死体が人狼ではないという事実を物語っていたのだ。ここは人狼の設定がうまく活きているのと同時に盲点として見落としやすいポイントなのでミステリとして秀逸だと評価している。
ミステリにおいて顔が潰されたり頭部が切断され持ち去られた死体を「顔のない死体」と俗に呼び、そういった死体が作中で出た場合はまず被害者と加害者の入れ替わりを考えるのが定石なのだが、本作だとノラとルイーゼの相似が前面に出ているためそっちの入れ替わりが目立って前の三件の被害者の入れ替わりに気づきにくい構成になっているし、ホイレンドルフの被害者が検死で本人だと証明されていることや、人狼側に入れ替わるメリットが(一見すると)ないため、ノラとルイーゼの入れ替わり※3に気づいた人はいても、前三件の被害者の入れ替わりトリックにまで辿り着けた人は少ないのではないだろうか。
そして二つの村で起こった事件なので当然複数犯の可能性や、人狼村での被害者が散弾銃で殺害されたことから人間が殺害に関与している可能性も出てくる訳だが、前述した通り人間が人狼の少女を撃ったとしたら被害者が真正面から撃たれているのは不自然だし、地下洞窟にいた斑蛾の大群が人間が犯行に関与していないことの証拠になっていて、きちんと別解が潰されているのも見逃せないポイントだ。
ノラの犯行動機となった血の儀式に関してはホイレンドルフの村長が10話でキンズフューラーについて語っていたし、人狼村の少女が巫女として首に下げていたネックレスが子宮を象ったものであるのもヒントになっている。10代前半の少女が狙われた理由は10代前半に初経(初潮)が見られる、つまり子どもを産める身体になるからであり、だからこそノラは少女たちを早いうちに逃がす必要があると考えたのだろう。
前回の感想記事で私は「痛み」という点が今回の事件の動機に関わると述べたが、その痛みというのは女性の痛み(生理や妊娠・出産といった痛み)を指しており、強い個体を生み出すため何体ものオスと性交渉を持つことになれば、当然身体に尋常でない負担がかかるし、医療従事者のいない人狼の村だから下手すれば死ぬことにもなりかねない。昔の出産はそれだけ命がけなのだから、何体もの子供を産むとなるとそれだけ死のリスクも高まる。ましてやその儀式を10代前半の完全に発達していない身体で行えばどうなるかなど想像したくないことだ。オスの人狼たちは、メスが抱えるこの痛みに鈍感であり理解しなかった、その歪みが今回の事件の原因の一つであることは確かだ。
※1:原作者のツイートで知ったが、今回のトリックの元ネタとなる作品はエーリッヒ・ケストナーの小説『ふたりのロッテ』だそうで、『ふたりのロッテ』では本作と同じルイーゼという少女が登場する。
※2:ちなみに原作では部屋に入ったグスタフが人狼を追うためわざわざ玄関から外へ出た描写があり、人間態で窓から出られないことがさり気なく提示されていた。
※3:人間村と人狼村に交流がないこと・地下道と地底湖の存在・二つの村の活動時間が昼夜逆であること等に加えて、人間村にいた時に静句はグスタフの家に入っておらずルイーゼの肖像画を見ていなかったのも、入れ替わりトリック成功の一因である。公式HPのキャラクター紹介の項でノラは「お寝坊さんな一面」があると記されているが、これも一人二役による二重生活の伏線になっていたのだ。
累と化したノラ
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
今回の事件における一人二役トリックや死体の入れ替え自体は特別珍しいトリックではないし、トリックだけを抜き出した所で本作の面白さは語れない。この人狼編で何より特筆すべきは、被害者であるルイーゼが共犯としてノラの犯行計画に加担していたことであり、それがミステリとしての意外性だけでなく物語としてのドラマ性に大きく貢献しているのだ。
かつて喰い口減らしのため両親から捨てられたルイーゼは村での自分の居場所を獲得するために自分を助けてくれたユッテを人狼として告発。しかしそれは「村の守り神」という偶像として扱われるという点では差別されていることに変わりはなく、ルイーゼはそんな村や両親に愛想を尽かすこととなった。
ユッテに対する贖罪とホイレンドルフへの嫌悪感、これがルイーゼが共犯になった動機であり、ノラは人狼の女たちを解放しヴォルフィンヘーレの因習を崩壊させることを狙って二つの村で少女連続殺害事件を決行、二つの村を衝突させることで両村それぞれの歪みを崩壊させようとした、ということになる。
原作では事件の真相を聞いた津軽が落語の「粗忽長屋」を思い出したが、私は今回の事件は日本の怪談話である「累(かさね)」とリンクする要素が多いのではないかと思った。
累の怪談は現在の茨城県を舞台にした物語。昔、与右衛門という百姓の家には後妻であるお杉と、その連れ子である助(すけ)という娘がいた。この助は顔が醜く足が不自由であったため与右衛門は助を嫌い、ある日与右衛門は助を川へ投げ捨て殺してしまう。翌年、与右衛門とお杉の間に女の子が産まれ「累(るい)」という名が付けられたが、その子の顔は殺した助に瓜二つであり、村人たちは「助がかさなって生まれて来た」とささやき、その子は「かさね」と呼ばれるようになる。
やがて累の両親が死に、累は谷五郎という男を婿に迎え入れるが、財産目当ての谷五郎は累を川に突き落として殺害、他の好きな娘と結婚する。しかし後妻として迎えた女は次々と病気で亡くなっていき、6番目の妻が生んだ娘の菊に取り憑いた累がようやく谷五郎への恨みを語る。谷五郎は謝罪したが菊の身体に取り憑いた累は出ていこうとしないので、祐天上人が累を成仏させ、またその遠因ともなった助の魂も同様に成仏させたという。
以上の物語は「累ヶ淵」というタイトルで『死霊解脱物語聞書』に収録されている。この怪談をベースにした落語や歌舞伎があるくらいだから、日本の怪談ではかなりメジャーで聞いたことがある人も多いと思う。助が足が不自由な娘であるという点は正に本作のルイーゼと同じであり、親から疎まれていた点も共通する。
私と同じくアンファルを視聴している闇鍋はにわさんの11話の感想でヴォルフィンヘーレがあの世のような場所であると述べている。闇鍋さんのアイデアから派生してこのノラとルイーゼの犯罪について考えるが、ルイーゼはグスタフ夫妻に捨てられユッテを告発した頃からもうこの世の住人として生きていなかったと言える。肉体は生きていたとはいえ、村人や両親から腫れ物扱いされ距離をとられていたのだから、その魂と存在はあの世に行っていたも同然なのだ。
そして月日は経ち、一年半前にノラとルイーゼは入れ替わる。ここでルイーゼは地下洞窟内に監禁されるが、地下は古代日本において根の国と称される場所であり、つまりあの世を意味する。ここでルイーゼは完全に現世と縁を断ちあの世の住人となった訳だが、反対にノラは人間にとってのあの世とでも言うべきヴォルフィンヘーレから地下を経由してホイレンドルフに向かい、そこでルイーゼとして二重生活を送る。ヴォルフィンヘーレや地下洞窟があの世(根の国)を象徴するならば、それをつなぐ地下道は黄泉平坂と言った所だろう。
ノラが主犯とはいえ、ルイーゼになりすました彼女はルイーゼの意志を継承している者であり、直接関係のないホイレンドルフの少女を殺すというのは累の怨霊が谷五郎の後妻を次々と呪い殺すのと似ている。ルイーゼの意志を受け継いだノラは、さながら助の生まれ変わりである累そのものだ。
瀉血としての謎解き
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
鴉夜による謎解きは最後に津軽が指摘したように早い段階からルイーゼの入れ替わりに気づいていたにもかかわらず意図的に真相を伏せていたと思われるフシがある。入れ替わりに気づかなかった両親や車いすの背中側の持ち手のキレイさから、ルイーゼが不遇な扱いを受けていたことを読み取り、それが事件の遠因と判断した鴉夜は、二つの村の衝突を敢えて止めずに滅びない程度に復讐の後押しをしたということになる。動機に関してはノラの方の動機はギリギリまで気づかなかったのであくまでもルイーゼ側に加担したということになるが、この下りで私が思ったのは鴉夜は探偵として無血での解決が必ずしも正解ではないという価値観を抱いているということだろうか。
人間にしろ怪物にしろ、口で言っても理解出来ない(或いは理解しようとしない)輩というのは往々にしてどこの世界にもいるもので、身をもって知らないと目が覚めない者も多い。30年も生きていない私ですらそう感じる時があるのだから、900年以上生きて来た鴉夜にしたらそれは当然の理というものだろう。言葉だけで糾弾する程度では二つの村に染みついた歪みは治らないし、人間と人狼、両者の痛みに対する鈍感さを少しでも是正するには血を流しその痛み・苦しみを身をもって知るべきであると判断したから、鴉夜は敢えて二つの村の衝突を見逃した。そう考えるとこれは一種の「瀉血」と言えるのではないだろうか?
瀉血(しゃけつ)はヨーロッパやアメリカで行われた治療法の一つで、体外へと血を排出することで血と共に体内の有害物・不要物が流れ出し、病気の症状が改善されると信じられていた。現在では多血症やC型肝炎など一部の病気において用いられる手法であり、血を流せば体内の有害物まで出ていくというのは迷信である。
この瀉血でふと思い出したが、横溝正史が生み出した名探偵・金田一耕助が殺人防御率が低いと揶揄される探偵であるにもかかわらず名探偵として現代でも支持されているのは、金田一が関わる事件がいずれも未然に防いでしまった場合、それは根本的な部分での解決にはならないからだと私は思っていて、淀んだ血(過去の因縁や忌まわしき風習など)を流させることによって未来にその悲劇を持ち越さない、今の世代で完全に悲劇の連鎖を断ち切るという意味合いもあるから、作中であれだけの犠牲者が出ても金田一は名探偵でいられると私は考えているのだ。金田一が狙ってやってないとはいえ、殺人の悲劇が瀉血としての効果をあげているから、物語は後味良く終われるし、そこに横溝ミステリ独特の魅力があると私は考えている。
(勿論、メタ的に考えれば連続殺人でないとミステリとして面白くないという理由もあるのだけど…)
総評
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
以上で最終回の感想を終えるが、総評に移る前にまず第三章「人狼」編のまとめ感想を言っておくと、シリーズ最長(約480頁)の物語を約20分×5話で描くという難題を見事にやり遂げたことはまず評価しなければならない。勿論尺の都合でカットされた描写は第二章よりもずっと多いけれど、本作の肝となる事件と謎解き、そして怪物と人間の大混戦はキチンと押さえて映像化されており、印象に残る場面もあって原作を読んで内容を知っていても新鮮な気持ちで視聴することが出来た。特にこの三章はまだコミカライズされていない話なので、人狼やホイレンドルフの村人がどんな姿で登場するのかも気になっていたポイントだったが、そのビジュアルから原作を読んだ時には思いつかなかった感想が出て来たので、感想・解説を書くのもそれほど困らなかったかなと思う。
ではここから作品全体の総評を語る。本作は19世紀末のヨーロッパが舞台であり、題材となる怪物や怪人・探偵も19世紀から20世紀にかけて発表された怪奇小説や探偵小説のキャラクターを用いている。この時代に生まれたミステリやホラーは今もなお多くの作品に影響を与えるエポックメイキングとしての名作・傑作ばかりが揃っており、正に大衆文学や怪奇小説の黄金時代だった。そんな時代の作品群をベースにしているのだからまず作品としての下地が盤石というか、「その題材を元に本格ミステリをやったらそりゃ面白くなるわな」という感じで怪物をお題にした特殊設定ミステリとして実に隙がないし、そこはロジックを重視したミステリを書く青崎氏の力量の高さがうかがえる部分だ。
勿論本作は先人の作品群に頼りきった作品ではなく、輪堂鴉夜・真打津軽・馳井静句の三人組による掛け合いや会話劇としての面白さも追求されており、日本文学の一つである落語が西洋を舞台にした物語に組み込まれているという所も注目しなければならない。
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
特に鴉夜と津軽のコンビ、そして鴉夜に代わって津軽に辛辣かつ強烈なツッコミをする静句の関係性は日本テレビで放送されている「笑点」を彷彿とさせる。笑点と言えば司会がお題を出して、それに対して噺家たちがうまい回答をするという大喜利のコーナーがある。そこでは回答者が時折司会を不謹慎にイジって座布団を座布団運びの山田隆夫に全部没収される※4というお馴染みの展開があり、特に今は亡き桂歌丸と三遊亭円楽によるバトルは私もよく見ていたので、本作で鴉夜が生首であることを元にしたイジり(生首ジョーク)を次々と出してくる津軽と鴉夜の関係は笑点の司会と回答者の関係に似ているなと思ったし、「静句、後で津軽をぶん殴っておけ」という鴉夜の指示は笑点における「山田君、〇〇さんの座布団全部持っていきなさい」という司会の指示を見ているようで、ミステリとしての面白さとはまた違うファルスとしての部分もこういった先行となる演芸によって支えられていたのだなと改めて思った。
言うまでもなくこの生首ジョークは身体欠損をイジっているのだからジョークとしては不謹慎で本来なら不快感を覚える人が出てきてもおかしくない所なのにそれがないというのは、津軽もまたある種の欠損者であり怪物を殺す鬼混じりという被差別民であるから、そこに健常者が欠損者をイジるいやらしさが感じられないのだろう。鴉夜と津軽は割れ鍋に綴じ蓋、欠けているからピタリとはまる関係性であり、それは「欠けているから分かり合える」という薄っぺらい標語や綺麗ごとめいた関係ではない。三人で旅をしないことには彼らの存在意義やアイデンティティは消え失せ、残る選択肢は「死」のみである。それは1話の段階で視聴者が既に見ていることだ。
そしてこのシリーズは怪物を扱っているので「怪物とは何か?」という定義についても私はこの度のアンファル感想で色々と語ってきたが、日本の妖怪や西洋の怪物・精霊・悪魔といったものを図鑑なんかで読むと、人間の思想の幅広さや生命の多様性に触れることが出来て面白いなと思うし、その複雑さにこそ人間が人間として生きていくためのヒントが隠されていると私は常々考えているのだ。
しかし、社会や経済といったものは複雑さを嫌う。サービスは常に同じ量・同じ質で毎日提供しないといけないし、政治家も民衆が同じ思想を持っていればいるほど統治しやすくなる。今社会は性の多様性や働き方改革といったことを目指してはいるけれど、本音は人もモノも均質的であった方が扱いやすいしイレギュラーは出来るだけ排除したいという思いが経済を動かす者の中にはいると思う。実際、本作の舞台となった19世紀末のイギリスは働かずとも暮らしていける上流階級、貧困にあえぐ下流階級、そしてその中間の中流階級という三層に大きく分かれており、街の東西で貧富の差が歴然と表れていたというのは5話の感想記事でも言及した通りだ。
経済が発展し国が豊かになればなるほど、社会はより単純でわかりやすい図式となり、その階級に合わせた生き方をしないと社会と適応出来ないから個人的な欲求や願望は抑圧されることとなった。そうやって均質化する社会から排除されたもの、イレギュラーとみなされたものこそが怪物の源であり、こういった社会背景が19世紀末の怪奇文学をヒットさせる土壌になったのだ。
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
本作で登場する保険機構ロイスは、正に均質化を求める経済社会を代表する組織であり、顧客の財産を守る名目でイレギュラーな存在である怪物を駆除する諮問警備部を保持しているが、怪物を駆除しているようでその実は本来人間が持っている多様性を駆除し、色とりどりでカラフルな思想を一律の白色に変えてしまう危険な組織なのだ。怪物であるはずの〈夜宴〉や〈鳥籠使い〉一行に人間性を感じ、逆に人間代表のロイスに怪物以上のおぞましさを感じるのはそのためである。
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
そんなレギュラーとしての人間、イレギュラーとしての怪物を考える上で、本作における真打津軽は色々と示唆に富んだキャラだったと私は思っている。彼は最終回でも言っていたように「馬鹿をやるのが仕事」で、落語やジョークで鴉夜を楽しませるのが彼の役目の一つであることは視聴者なら既にご存じの通りだし、鬼殺しとしての戦闘スタイルは突拍子がないというか、相手の意表を突いたものが多い。とはいえ非論理的で無茶苦茶な男という訳ではなく、意外に計算高いし合理的な面もあることは12話でロイスを引きはがすために〈夜宴〉を誘導したことから見ても明らかである。
私の分析だと、津軽は賢くないだけで合理性に関しては鴉夜と引けを取らないのではないかと思っているし、合理性が突き抜けているが故に時としてそれが怪物のような発想に見えてしまう部分がある。別にそれは鬼の血が混じったからそうなった訳ではないだろうし、1話で鴉夜は「生まれながらの人外」と津軽を評しているから、合理性こそ津軽の個性であると同時に彼の怪物的要素でもあるのだ。本来なら人間性として評される合理的な性格が逆に彼の異常性を物語っているのだが、では津軽の人間性を示すものは何かというと落語をはじめとする芸の道にあるのではないだろうか。
芸人というと1話の感想記事でも言及したように当時の職業としては卑しい仕事という扱いを受けることもあったし、合理性という面で考えれば芸人に金を払うくらいなら食費・生活費に充てた方がマシという考えがあってもおかしくない。事実、コロナ禍で芸能・芸術は不要不急という扱いを受けた過去があるくらいだから、芸の道というのは非合理的な要素が強い。しかし、合理性の鬼とでも言うべき津軽はそれを摂取することで人間性というものを担保していたのではないだろうか、というのが私の仮説である。
そう考えたのは津軽が鬼殺しとして活動していた時期を描いた原作4巻のエピソードを読んでいた時で、この時に私は津軽は鬼の血が混ざる前からある意味怪物的存在であり、落語という芸能を摂取することで人間性を保っていたのではないかという考えに至った。1話で津軽は鴉夜の唾液を摂取することで免疫を高め、鬼に意識が呑まれぬようにしていたが、実は鴉夜と出会う前にもう津軽は自分の中の鬼を抑制する行為をしていたのだ。鬼の血と鴉夜の唾液による免疫が表で拮抗していた裏で、合理と非合理というもう一つの拮抗があった訳であり、津軽はその二つの間を行き来するマージナルマン(境界人)だったということになる。だから人と怪物の間を行き来するという点で津軽は「ゲゲゲの鬼太郎」におけるねずみ男と同じポジションではないかな?と私は思った。
ねずみ男も人と妖怪の両方の面を持った半妖怪でどっち付かずの存在として描かれているし、津軽も怪物の血が流れていながら怪物を殺すという点で人間と怪物の両者から疎まれ忌み嫌われる存在だ。しかしねずみ男や津軽といったマージナルマンが私たちに教えてくれるのは、私たちの社会は正常と異常を分けたり、弱い者・強い者、勝ち組・負け組といった区分けや棲み分け、レッテル貼りなんかをやっているけど、それは所詮人間の主観や都合で決めているだけで本当は誰にもそんな区別は出来ない。「住む世界が違う」という言葉があるけどその世界は勝手に人間が分けているだけで本当は別にどこに住もうが問題はないし、怪物性というのも人間側の一方的な尺度で決めているだけの話だ。
だから私もこれまで散々人間性とか怪物性の話をしてきたけど、本当はそんなものなど存在しない。全ては自然という大きな括りによってそれはまとめられるものであり、私たち人間社会が自然界における混沌を受け入れられないから、整理整頓をして名前を付けて分類をして、私たちの頭脳で理解出来るようにしたというだけのことなのだ。そして理解出来ないものが怪物や幽霊としてオカルトという箱の中にぶち込まれて来た。そうして今日の人間社会は成り立っているのである。
まぁ、原作者の青崎氏はこんな高尚なことを考えて本作を書いた訳ではないだろうし、あくまでも「アンデッドガール・マーダーファルス」は謎解きありバトルありのエンタメ活劇として受け取ればそれで良いが、最後に津軽が崖の上から放った「やっほー!」という山びこの声がホイレンドルフやヴォルフィンヘーレだけでなく遠方にいるはずのルパンやホームズ、切り裂きジャックにまで届いているかのようなあの演出について深読みすると、先ほどから言っているように人間と怪物はお互いに相容れぬ存在として壁を作り住む場所を分けて生きているけど、本当はそんな壁など存在しない。人間も怪物も探偵も怪人も怪盗も、全ては地続きであり隔絶した存在ではない。全てはつながっておりだからこそ人間と怪物の間を行き来する津軽の声が届いたのだという風に解釈出来るのではないだろうか?
© 青崎有吾・講談社/鳥籠使い一行
そして津軽の山びこは生首となって鳥籠の中に入らざるを得なくなった、つまりは鳥籠の内と外という境界が出来た鴉夜さえも驚嘆させる。鳥籠とそれをおおうベールによって隔絶された鴉夜の世界は、津軽のマージナルマンとしての勢いにより取っ払われ、その世界の複雑さと混沌とした様相をポジティブな笑劇(ファルス)として彼女は受け入れた。この物語の結末を清々しい心持ちで見ることが出来たのは、この世界の混沌をポジティブに前向きに描いたことも大きいだろう。
※4:そんな座布団没収の中でも歌丸師匠は全員の座布団を全て没収することがあり、それは俗に「歌丸ジェノサイド」として知られている。(↓)
聞くも涙、語るも涙の事件がありました…。 #shorts - YouTube
さいごに
さて、これで私のアンファル感想・解説を終える。原作はまだ映像化されていないのが1巻の「人造人間」のエピソードと4巻の5つのエピソード、計6つのエピソードになるが、いずれも時間を空けずにアニメでやるとなると過去回想、つまりはエピソード0という形でやるしかないので、人狼編以降の物語は原作者がどれだけ執筆出来るかにかかっている。一応原作4巻の末尾には次のエピソードが「秘薬」であると予告されており、4巻が今年発売されたから5巻は早くても来年、遅いと数年先に刊行されることになりそうだ。恐らく次に出て来るのは「ジキル博士とハイド氏」と予想するが、また最新刊が発売された際に、当ブログで5巻の感想が書くことが出来たら良いなと思っているのでその時はまたよろしくお願いしますね。勿論、アニメの続編も待ってますよ!